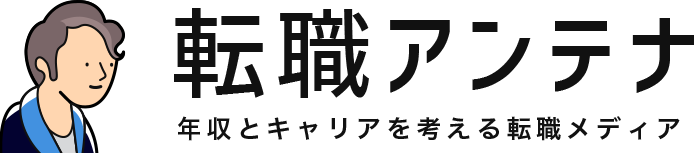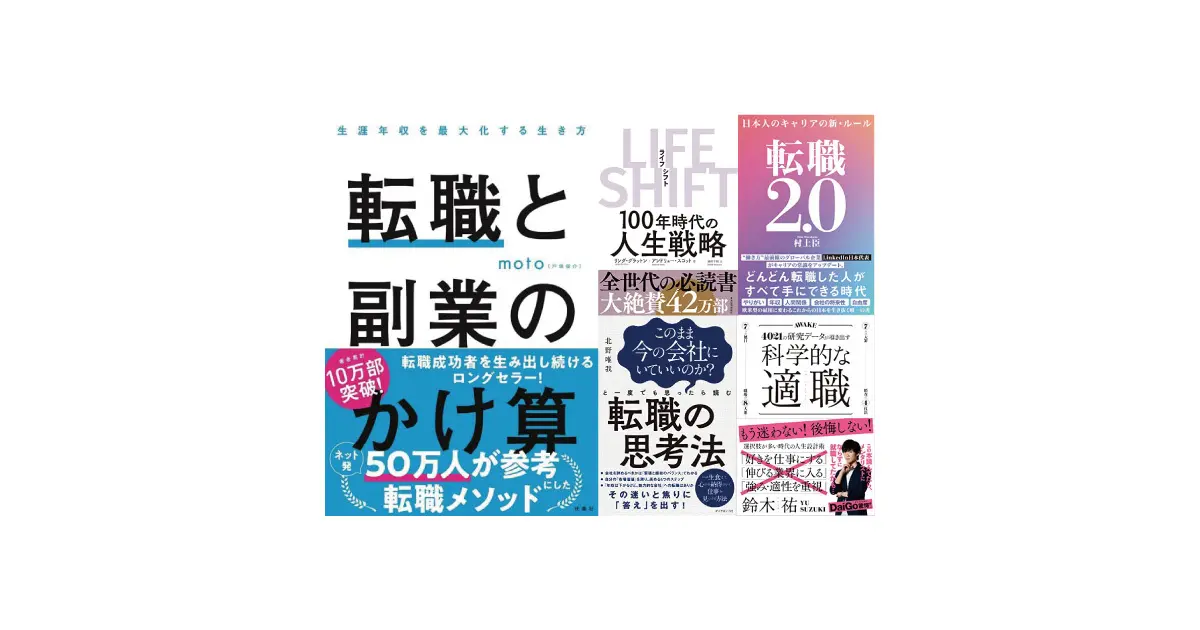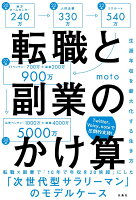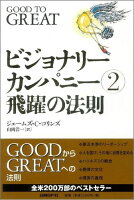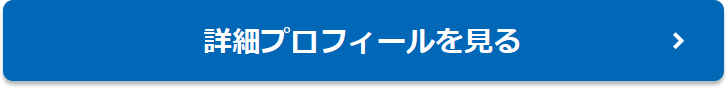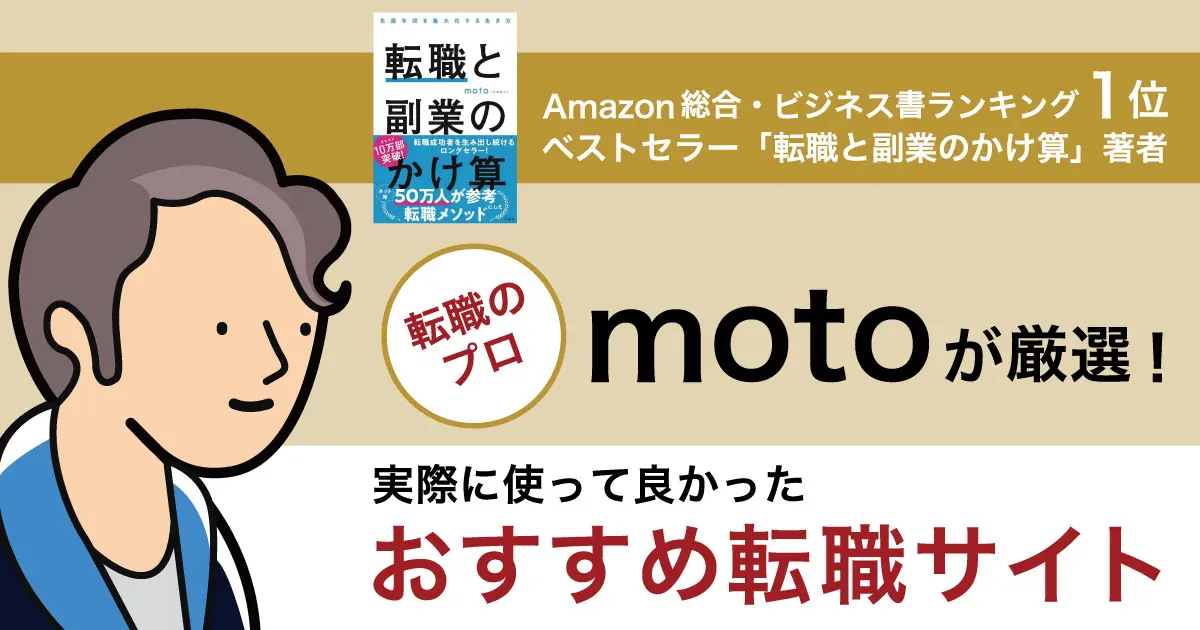目次
おすすめのビジネス書のベストセラーをランキングで紹介
この記事は書籍『転職と副業のかけ算』の著者であるmoto(戸塚俊介)が、おすすめのビジネス書を年代別にご紹介します。
本記事の筆者であるmotoは、X(旧Twitter)@moto_recruitフォロワー数が12万人を超えるビジネスインフルエンサーです。書籍『転職と副業のかけ算』はAmazonランキングで総合1位のベストセラーとなっています。
筆者のキャリアやこれまでの実績についてはプロフィールをご覧ください。
※キャリアや転職に関するおすすめ書籍も合わせてご覧ください。
全ての年代におすすめのロングセラーのビジネス書ランキング
まずはじめに、すべての年代におすすめのロングセラービジネス書をランキングでご紹介します。
1:7つの習慣
おすすめ度:★★★★★
全世界で4000万部、日本でも240万部を超える大ベストセラーです。僕は仕事やキャリアなど、何かに迷った時に読み返しています。
すべての時代と人種、年齢や性別を問わず、どんな人にも当てはまる普遍的な原則で、ビジネスの場でも応用できます。重厚な本なので、長期休みのタイミングなどで読んでみてください。
2:嫌われる勇気
おすすめ度:★★★★★
日本発で世界累計500万部超の大ベストセラーを記録するアドラー心理学の入門解説書的な作品です。「すべての悩みは対人関係の悩みである」がベースにあり、哲人と青年の対話をなぞっていくうちに、幸せな人生を築くヒントが随所で得られます。悩みをシンプルに切り分けられて、スッキリとした読後感が味わえる本です。
3:伝え方が9割
おすすめ度:★★★★★
コピーライターの佐々木圭一氏が編み出した「伝え方」に特化しているベストセラー書籍です。「心を動かすコトバには、法則がある」とあるように、伝え方の技術を身につけておけば、相手の受け取り方が一変するまであります。仕事からプライベートのあらゆる場面でコミュニケーションが一段階磨かれるので、読んでおいて損はないです。
4:転職と副業のかけ算
私が書いた一冊です。おかげさまでロングセラーとなり10万部を超えました。
新卒で地方ホームセンターへ入社し、転職と副業を通じて年収240万から年収4,000万に至るまでの実体験を書きました。おかげさまでAmazon総合ランキング1位、Amazonビジネス書ランキング1位を獲得し、ビジネス本大賞2020にもノミネートされました。
僕は、本書を通じて「転職して年収を上げたい」「サラリーマンとしての市場価値を上げたい」「給料以外の収入が欲しい」「老後のお金の不安を減らしたい」と考える人の一つのロールモデルになれたらと思っています。
これからの時代は、会社も組織も自分のキャリアを保証してくれません。自分の身は自分で守るしかないのです。
本書の内容の一部は「【無料公開】著者が語る『転職と副業のかけ算-生涯年収を最大化する生き方-』」で公開しています。
働く中でどのように思考して年収を上げたか?について具体的に書いてます。「給与はもらうものではなく、稼ぐもの」という考え方に興味がある人は、ぜひ読んでみてください。
2冊目となる『WORK-価値ある人材こそ生き残る-(日経BP)』も2022年1月に発売しているので、合わせて読んでみてください。
20代におすすめビジネス書ランキング
業界、職種問わず20代におすすめのビジネス書をご紹介します。下記のビジネス書はすべての20代のビジネスマンにおすすめです。
1:WORK
おすすめ度:★★★★★
手前味噌ですが、私が書いた一冊です。これまでのキャリアの中で失敗から学んだことについて書いています。
ベストセラーとなった前作『転職と副業のかけ算』は「転職」や「副業」という手段を通じて“個人の価値を最大化する”というテーマでしたが、本作は「仕事との向き合い方」をテーマにしています。
本作では、僕の過去の経験から「成果との向き合い方」や「組織で働く上で持つべき視点」、「自分の価値を上げる働き方に必要な思考法」など、会社員として働く中で得た考え方を70項目に分けて書き出しています。
書籍の詳細はこちらをご覧ください。
2:未来に先回りする思考法
おすすめ度:★★★★★
未来に先回りすることができる0.1%の人たちを調べていくと、99.9%の人とはまったく違った思考法を用いて、未来を見通していることがわかりました。両者を分けているのは、パターンを認識する能力です。
広告系ベンチャーの事業部長からもらったメタップス代表取締役の佐藤航陽氏のビジネス書。めちゃくちゃ面白かったです。
この本では、タイトルの通り「未来についてどう自分の頭で考えて、答えを見つけるか」がめちゃくちゃわかりやすく説明されています。
文章自体がキレキレで世の中を見る視点が鋭く、読んでいて爽快感を味わえる本は最近なかったので、本当に面白く読めました。
3:なぜハーバード・ビジネス・スクールでは営業を教えてくれないのか?
おすすめ度:★★★★・
営業とは、ものを売ることではなく、自分を売り込むだと考えている。お客様は商品を買うのではなく、信頼できるあなたが売っているもの、つまりあなた自身を買うのだ。
黄色い看板を掲げる激安が売りの大手小売業界社長にお薦めいただきました。
ハーバードMBAで教育を受けた英国人のジャーナリストが、モロッコの絨毯商人、日本のトップ生保営業マン、イギリスのテレビ通販セールス、米国の美術商などを取材して、彼らの生い立ちや「成功の秘訣」について書かれたビジネス書です。
僕自身、営業のビジネス書は何冊か読んできましたが、ビジネスに関する学びは「リアルな事例」が大切だと思っており、その点でこの本は非常に参考になりました。営業マンにおすすめできるビジネス書です。
4:確率思考の戦略論
おすすめ度:★★★★★
「ビジネス戦略の成否は『確率』で決まっている。そしてその確率はある程度まで操作することができる」
2010年に730万人だったUSJの年間来場者数を5年間で1,390万人まで増加させた実績を持つ著者の一冊。5年間で来場者数を倍増させたのは「偶然ではなく計算されていた」というマーケティングのビジネス書。
価格が少し高いのがネックですが(3,000円超えます)、ビジネスマンなら必読の一冊です。タイトルの通り「数学マーケティング」なので、難しい数式も出てきますが、わからなくても読めますし思考が深まるビジネス書だと思います。
5:アナロジー思考
おすすめ度:★★★★・
エス・エム・エスの役員の方にもらった一冊。
何か新しい経験するとき、似たような過去の経験から類推(アナロジー)して「あれと同じ感じかな?」と考えたりすることがありますが、それこそが「アナロジー思考」です。
アイデアは「これまでどこかにあったものの組合せ」でしかないため、何か新しいことを考えるには「どう組み合わせるか」という思考が必要になってきます。この思考は、日常生活でも非常に役立ちます。
様々な事例から丁寧に解説してくれるので、普段の仕事でいろんな側面から物事を考えたい人におすすめするビジネス書です。
6:エッセンシャル思考
おすすめ度:★★★★・
クライアントであるITベンチャーの社長から頂いた一冊。日々の作業に忙殺されがちな人や、周囲に流されやすい人におすすめです。
エッセンシャル思考とは「重要なことだけ」を行うための考え方のこと指します。
非エッセンシャル思考の人は、トレードオフが必要な状況で「どうすれば両方できるか?」と考える。だがエッセンシャル思考の人は、「どの問題を引き受けるか?」と考える
「選ぶことを選ぶ」という言葉がとても印象的でした。「最小の時間で成果を最大にする」というのはすべてのビジネスマンに求められることだと思うので、読んで損はないです。とてもおすすめのビジネス書です。
30代におすすめのビジネス書ランキング
30代で大手企業に勤める会社員の方や、ベンチャー企業でマネジメントをしている人に人気のあったビジネス書をご紹介します。いずれも非常に読みやすい本なので、ビジネス書に慣れていない人にもおすすめです。
1:イシューからはじめよ
おすすめ度:★★★★・
外資コンサル出身でDeNAに勤める役員の方にもらったビジネス書。「労働時間なんてどうでもいい。価値のあるアウトプットが生まれればいい」というのが印象的でした。
これまでいろいろな問題解決系の本を読んできましたが、最もわかりやすくまとまっており、DeNAっぽい感じがしました。
問題を解く前に「解くべき問題を見極める」という考え方と「その具体的戦略」について詳しく書かれているので、実際の仕事の中でとても役立ちました。
2:HARD THINGS
おすすめ度:★★★★★
転職を考えていたときに人材広告を営むベンチャー企業の社長からもらったビジネス書。現実で起きた難題をどう解決してたか?がリアルに書かれています。
「社員をクビにするときの作法」や「親友を降格させる」、「クライアントから契約解除を言い渡されたときにどうしたか」など、本当にリアルで起こることばかりが書かれているので、自分ごととして読めた一冊でした。
経営者はどんな気持ちで仕事しているのか?について、真剣に知りたい人におすすめのビジネス書です。
3:ビジョナリーカンパニー②
おすすめ度:★★★★★
一般的な普通の会社がいかにして“偉大な企業”に変貌するかの違いやポイントが「飛躍の法則」としてまとめられています。
日々の小さな積み重ねにおいても、自分は何を意識して仕事をすればいいのか、どのようなリーダーが素晴らしい会社を築き上げることができるのか、という一歩上の視点を学べます。
40代におすすめのビジネス書ランキング
40代の大手企業の部長や事業本部長など、マネジメント層に人気のあったビジネス書です。
人事制度設計や研修などでも使われている本なので、人事だけでなく、組織を俯瞰する立場の方はぜひ読んでみてください。
1:学習する組織
おすすめ度:★★★★★
DeNAの役員の方から頂いたビジネス書です。ベンチャーに勤める方や、マネージャー職の人は必読だと思います。
「システム思考」という考え方を通して「自ら問題を解決していける組織」にしていくための知識や知恵が書かれており、非常に実用的です。
よくある自己啓発本と違って「何故問題が起こるのか」「どう対処すべきか」について、理論や経験に基づいて書かれているので、組織作りに関心がある人は読んでみてください。
2:なぜ人と組織は変われないのか
おすすめ度:★★★・・
リクルートに在籍していたときに人事の役員の方からもらった一冊。なぜ組織と個人は変われないのかについて、データや筆者の見識も踏まえて分かりやすく解説されているビジネス書です。
400ページを超えるボリュームがあるので、長期休暇などの時間があるときに読んでみてください。ボリュームは多いですが、本当に勉強になる内容なので、会社の合宿などにも使えると思います。
3:グロービス MBA組織と人材マネジメント
おすすめ度:★★★・・
上場しているベンチャー企業の役員の方からもらったビジネス書。人事は必読。「組織文化」「組織体制」「評価制度」などのシステムを通していかに組織を作り込んでいくか、ということが書かれています。
「戦略を実行するために組織はどうあるべきか」「人材の能力を最大限引き出すために人事制度はどうあるべきか」を学ぶことができる教科書的な本です。こちらも組織課題を抱えるすべての人に役立つと思います。
以上、おすすめビジネス書でした。
有り難いことに、僕自身も書籍を出す機会に恵まれ『転職と副業のかけ算』を出版し、おかげさまでAmazon総合・ビジネス書ランキング1位のベストセラーとなりました。
いずれもビジネスマンなら押さえておきたい点がたくさん書いてある本なので、時間のあるときに読んでみてください。
執筆者・監修者のmotoについて
![]()
moto
Follow @moto_recruit
起業家・著述家。実名は戸塚俊介。広告・人材・IT業界など8社へ転職。副業でmoto株式会社を起業し、上場企業へM&A。現在はHIRED株式会社(有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-313037)代表取締役。著書:『転職と副業のかけ算』(扶桑社)、『WORK』(日経BP)、YouTubeチャンネル:『motoの転職チャンネル』。