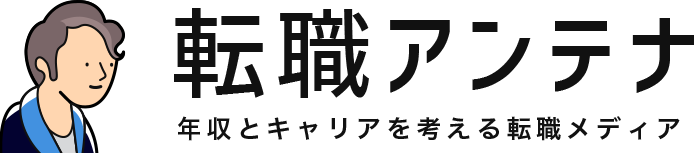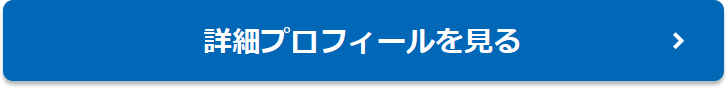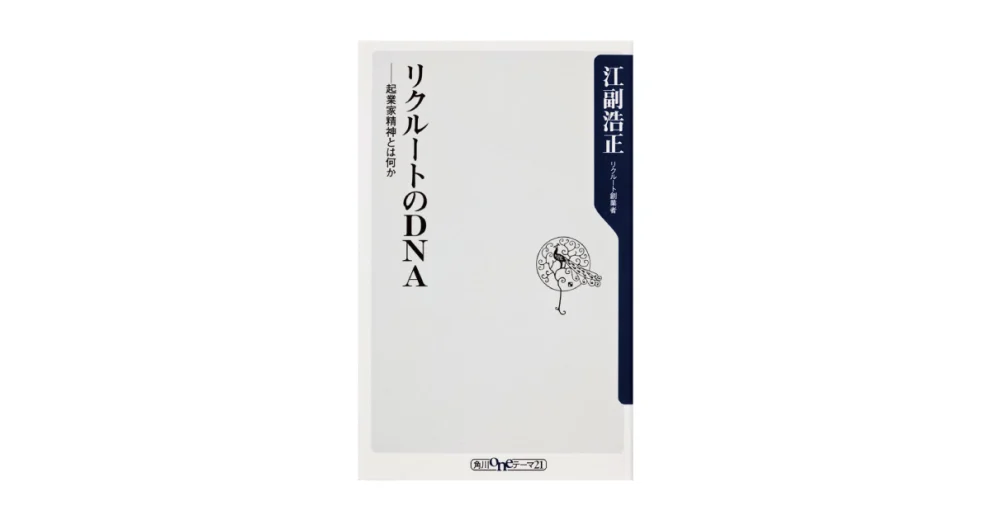
リクルートに在籍していた時、上司に「マネージャーになるためにはどんな能力が必要ですか?」と聞いたことがある。
僕は『「お前はどうしたいの?」リクルートで上司に“詰められた”話』にも書いたようにポンコツなリクルート社員だったため、マネージャーになることだけを目的に質問をしていた。
そんな愚かな質問に、当時の上司が僕に教えてくれたのが、リクルートの創業者である江副さんの言葉だった。マネージャーを目指す人や、マネージャーをやっている人はぜひ参考にしてほしい。
また、江副さんが新入社員に向けて書いた『リクルートの創業者「江副浩正」が新入社員へ贈った“12の言葉”』『マネージャーに贈る言葉20章』も本質的なメッセージなので、合わせて読んでみてほしい。
目次
マネジャーに贈る十章
【一】希望・勇気・愛情
未来への希望を抱き続けること。よい明日のために、今日すべきことはなし終えること。大切なものは勇気。「為さざる罪を問う」をリクルートのモットーとする。
利益や高い業績を求めるだけでなく、周囲の人々への思いやりや人への愛情も大切。高い成果の追求のために、人への思いやりを失えば、やがて周囲の人から敬遠されていくことを知って欲しい。
【二】ネットワークで仕事をすること
私はごく普通の才能しか持ち合わせていない。そのような私でも大きな仕事をしているのは、私が私自身の弱みを知っていて、自分の弱いところをカバーしてもらえる人とのネットワークを構築して、ともに働いて高い成果を上げるように、心がけてきたからである。
誰でも、周囲から信頼される良いネットワークを構築していけば、一人では難しいことが可能になる。ごく普通の人でも大きな仕事ができるのが、人が組織をつくる目的である。
【三】高い給与水準
リクルートは社員の給与水準の高い会社にする。高い報酬を得ることは働く人の誇りとなる。給与水準を高くするとともに、個人間の格差も大きくしていく。誤解のないように述べるが、給与の低い人がだめな人ということではない。
石庭で有名な龍安寺のつくばいに「吾 唯足知」(われただ足ることを知る)の文字が刻まれている。「知足のものは貧しいといえども富めり」という禅の言葉だが、給与が低くてもそれで心豊かな人もリクルートは必要としている。
【四】人は仕事を通じて学ぶ
「忙しすぎて考えるための時間がない。人は読書や思索にもっと時間を割くべきである」と言う人がいる。しかし、両者を分けて考えることは難しい。なぜなら、人を読書や思索に駆り立てる源泉が、仕事そのものの中にあるからである。
人が業績をあげようとする過程での勉強が、成長と密接に関連している。
【五】プレイングマネジャー
リクルートのマネジャーはプレイングマネジャーである。その関係は、高校野球のキャプテンとメンバーの関係と似た関係である。プレイングマネジャーが最も優秀なメンバーでなければ、メンバーはリーダーの指示通りに動いてくれない。
山本五十六の言葉に「やってみせ、やらせてみせて、褒めてやらねば、人は動かじ」というのがある。やって見せられない人は、リーダーシップを発揮できない。
【六】まず周囲に自らを語ること
マネジャーは、ともすればメンバーをよく理解することに熱心になりがちだが、それよりマネジャー自身の考え方、人格までもメンバーによく語り、自らを理解してもらうことが重要である。
周囲の人から「あの人は何を考えているのか分からない」と思われている人には、人はついていかない。
【七】数字に強いこと
マネジャーには、コンピュータやインターネットなど優れた道具を十分に駆使する能力を高めることが重要である。また、数字に強いこともマネジャーの主要な資格要件である。
数字に弱いマネジャーは、いずれマネジャーの一員に留まれなくなる。明日のより大きな利益を求めることがマネジメントには要求されている。今日の数字だけでなく、明日の数字も読み取る能力も重要である。
【八】努力の継続
マネジメントの能力は、音楽や絵画とは違って、生まれながらの才能によるものではなく、仕事についてから学び、努力を継続していくことで身につけていくもの。その証拠に、十代の優れた音楽家はいても、十代の優れた経営者はいない。
誰でも努力はする。問題は努力を継続できるか否かである。偉大なピアニストやバイオリニスト、偉大なスポーツマン、どの領域でも、秀でた業績を上げた人は、すべて練習に練習を重ね続けてきた人である。経営者も例外ではない。
【九】脅威と思われる事態の中に隠された発展の機会がある
事業が順調なときは、イノベーションやリエンジニアリングは行われにくいものである。事業あるいは個人が危機的な状況に置かれたときに、イノベーションは行われやすい。ピンチを迎えた時、それまでの常識から離れて、現状のピンチを打開しようとする。
そのようなときに、普段には出ない発想が生まれ、イノベーションが行われる。易経に「窮すれば変じ、変ずれば通じ、通じれば久し」とある。人は苦しくなると、とかく立ち止まりがちになる。自ら変ずることはつらくいて苦しい。だが、立ち止まっていると、やがて自滅していく。自らを変えれば、新しい道が開ける。
【十】リクルートは社会とともにある。
社内にしか人間関係を持とうとしない人がいる。そのような人が社員を動かして仕事をしていると、やがて会社は滅んでいく。社外の人との相互理解を持って、仕事を前に進めていくこと。
社外の勉強会に参加するとか、大学での就職セミナーの講演依頼、非常勤講師などの依頼、出版の依頼があれば、進んで受けること。政府の委員就任や経済団体からの委員就任の依頼があれば、時間を割いて受けるように。
リクルートは社会とともにある。社会のことを考えず、自らの利益だけを追求していてはいけない。社会への奉仕、国家への貢献というシチズンシップが大切である。
書籍『リクルートのDNA』
十章をご紹介したが、これは書籍『リクルートのDNA』にも書かれている。とても参考になるのでぜひ読んでみてほしい。
執筆者・監修者のmotoについて
![]()
moto
Follow @moto_recruit
起業家・著述家。実名は戸塚俊介。広告・人材・IT業界など8社へ転職。副業でmoto株式会社を起業し、上場企業へM&A。現在はHIRED株式会社(有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-313037)代表取締役。著書:『転職と副業のかけ算』(扶桑社)、『WORK』(日経BP)、YouTubeチャンネル:『motoの転職チャンネル』。