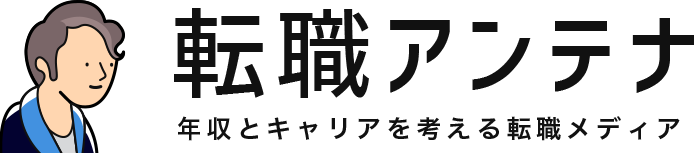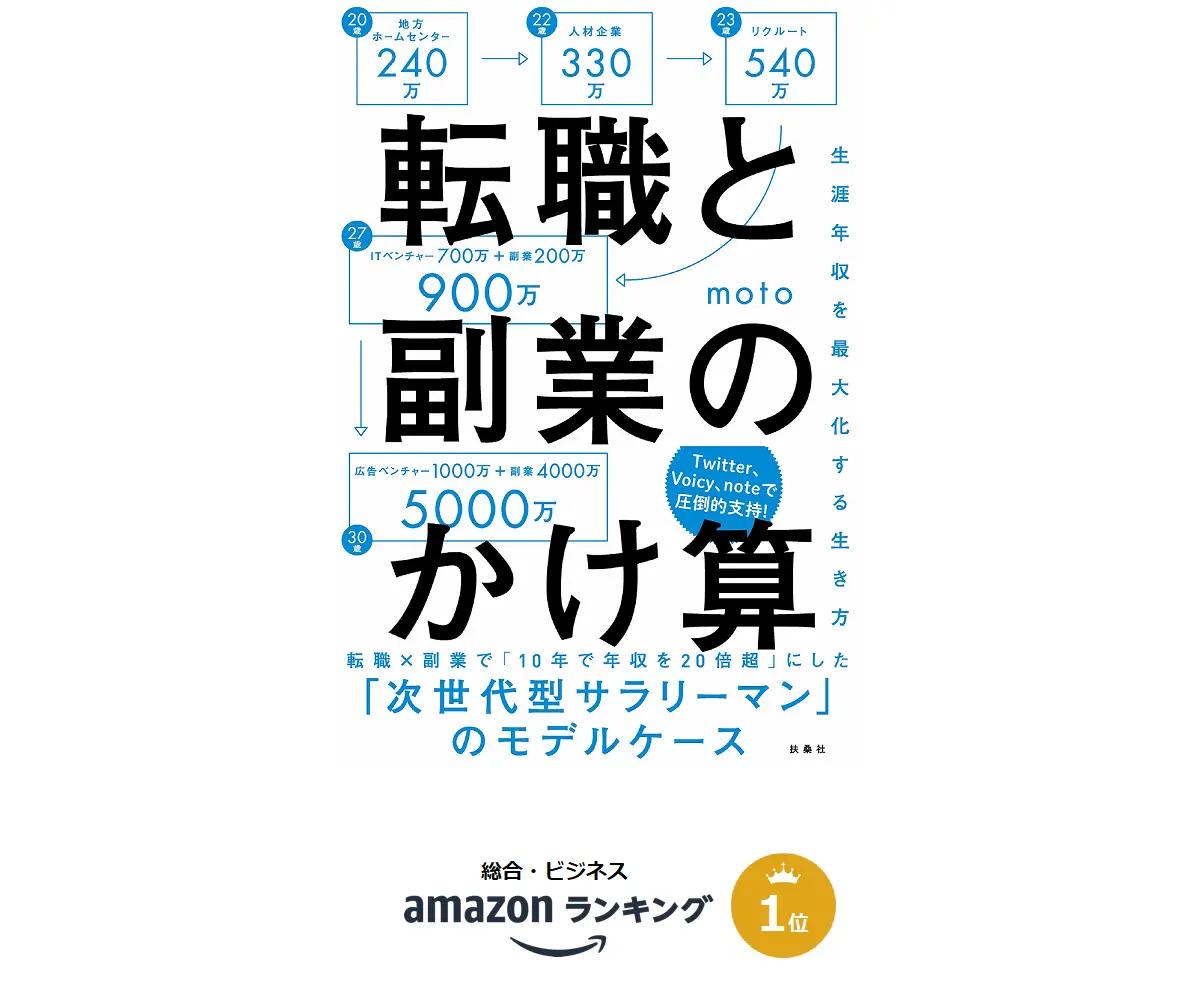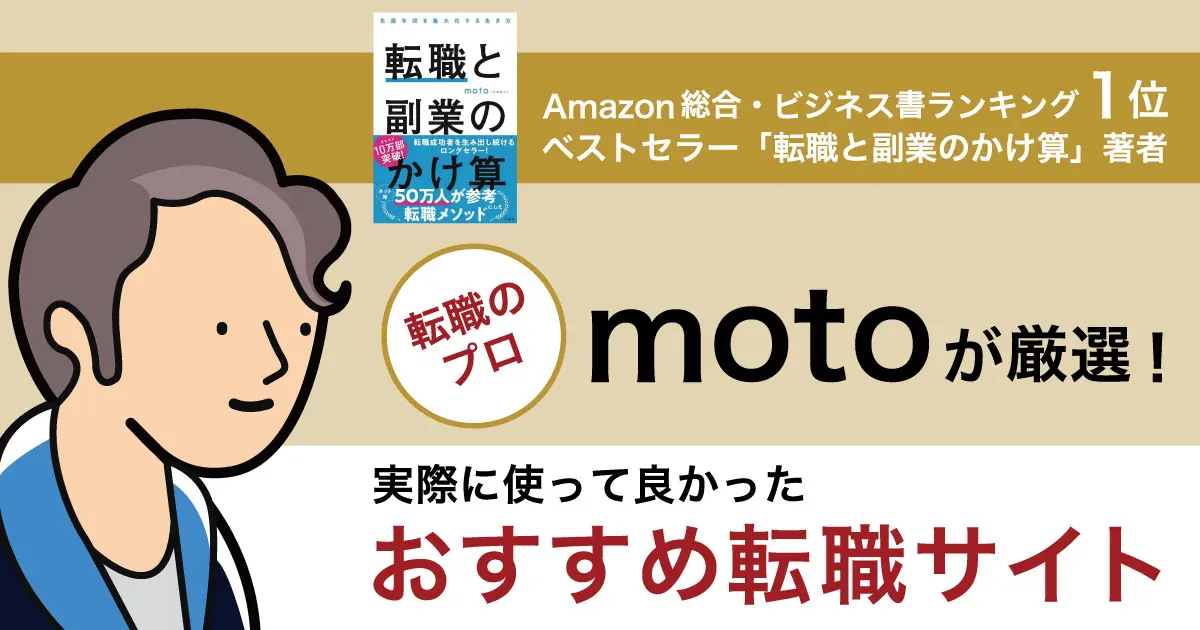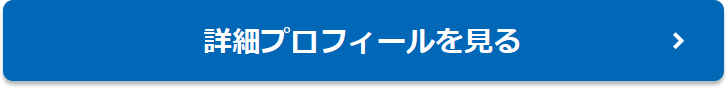TwitterのDMで転職の面接に関する質問が増えてきたため、今回は私が「面接する際に見ている3つのポイント」と「どういう人が面接で評価されるか?」についてお伝えします。
目次
転職の面接でよく聞かれる質問
仕事での立場上、就活生や転職者の面接をする機会があります。
過去に在籍していたリクルートやベンチャー企業では、営業のポジションにつきながら転職者の採用面接をしてきました。
私がどの採用ポジションにおいても、必ず見るようにしていたポイントは3つです。
- この人は“何が”できる人なのか?
- この人に“再現性”はあるのか?
- 情報を“どのように”見ている人なのか?
採用ポジションや採用要件によって見るポイントの角度の違いはありますが、私が面接でどのようなポイントを見ていたかを書いておきます。
面接対策しないと回答が難しい質問と回答
上記で伝えた面接官が見ているポイントは、面接対策をしておかないと回答が難しい質問です。ここではどのような点を見ているのかについて詳しく解説します。
質問1:あなたは何ができる人ですか?
転職の面接では「この人は、何ができる人なのか?」という点を見ています。面接する側と面接される転職者の認識でズレていることが多いのがこの質問です。
例えば「私は売上目標を120%で達成してきました。四半期の全社会議でMVPを獲得し、年間では社長賞も授賞しました!」という自己紹介をする人によく出会います。
「達成率120%という圧倒的な実績と、自社の社長にも認めてもらっている私は、誰よりも営業デキます!」という主旨を伝えたいのだと思いますが、面接する側が知りたいのは、結果ではなく「で、あなたは何ができる人なの?」です。
MVPや、社長賞も大きな評価や実績ですが、それはあくまで「社内の物差しにおける評価」なので「そうか! この人を採用したら売上が上がるかもしれない! おい君、彼は一体どこで!」とはなりません。
伝えるべきは結果のスゴさではなく「“どうやって”目標達成率を120%にしたのか?」という部分です。
面接では結果を推すよりも「目標に対して、自分がどんなアクションをしたのか」という点を伝えるのが鉄則です。プロジェクトの大きさや結果のスゴさより「自分が実行したアクションの深さと濃さ」が肝です。
具体的には「どんな目標があって」「その目標を達成するために何を考えて」「自分がどんなことをしたのか」を丁寧に話すこと。どんな相手にも、背景情報まで含めてわかりやすく話すことが大切です。
さらにいうと、自分に与えられた目標だけでなく「会社として目指している景色」まで踏まえて話ができると、もう一段高い評価につながります。
会社が目指している「上流部分」を見つつ、自分が行う「下流部分(手元のミッションと具体的なアクション)」を把握・実行して会社の成果につなげる行動ができる人は、とても評価が高いです。
会社が目指している上流部分から物事を捉える力は急には身につかないので、日頃の仕事の中で視座の高さを意識して仕事に取り組むのがおすすめです。
会社は組織なので、与えられた個人の目標を達成するだけでなく「組織としての目標」や「その目標を達成することで見える組織の風景」なども考えて行動できると、どの会社でも評価されると思います。
質問2:同じことをした場合、どうしますか?
転職の面接で見ている2つ目のポイントは「再現性」を考えられるか、という点です。
「何ができる人なのか?」がわかってくると「この人がうちに入社して、同じように活躍できるか?」という点を見ます。
商品や組織の形、価格もステークホルダーも違う環境の中で「前の会社と同じように活躍できる力があるのか?」という「再現力」はとても重視します。
僕は、いわゆる「市場価値」というのはこの部分にあると思っています。
「成果を出すプロセスで、何を考えて、何をしたか」だけでなく「その成果を出す経験を通じて得たことを、自分の血肉にできているか?」が自分の市場価値に大きく寄与します。
「もし仮に、もう一度同じ仕事をやるなら、どうやりますか?」と問われたときに「前回と同じことを、同じようにやって、前回と同じ成果を出す人」と「一度経験したことを活かして、効率よく、高い成果を出す人」では評価は大きく異なります。
面接官を勤めてきた経験上、「これまでのキャリアで経験したことを、この会社でどう活かせるか?」を解像度高く説明できる人ほど再現性は高い傾向にあります。
説明するにあたっては、新しい会社での仕事を「映像」で想像できるくらいまで情報収集し、映像の中で「あ、この部分は今までやってきたことが活かせそうだ」というポイントを絞って面接で訴求するのが良いです。
これまでの経験を自分の血肉とし、高いパフォーマンスで再現できる人は面接シーンに限らず市場での評価も高いです。
また、「成功体験だけ」を血肉とするのではなく、仕事を振り返ったときの失敗や後悔を「反省・内省」についても自分の経験に刻んでおくのが良いです。
面接を受けている会社に入社したら「これまで自分がやってきた経験」を「どのように活かして」「どんなパフォーマンスを出せるか」という「自分を採用するメリット」と「自分の企業貢献度」について、再現性を含めて説明できるようにしておくと、年収交渉などもしやすくなります。
質問3:あなたはどのように情報収集していますか?
面接で見ているポイント3つ目は「情報に対する見方」です。
「情報源」や「情報感度の高さ」はもちろんですが「面接者がその情報をどう見ているのか」や「その情報について自分がどう思い、どう発信するのか」について見てます。
「事実」と「感想」を分けて話せているか、「客観的に捉えられているか」など「情報に対するその人の捉え方、発信の仕方」でビジネス感度や日頃のインプット量を見てます。
こうした部分は日頃の積み重ねなので、付け焼き刃ではどうにもならないので「その人の素の部分」がよく見えます。
決してインプットの量を見るのではなく「そのインプットから、何を考えたのか?」を見ることで、その人の思考や思想がわかるようになります。
ビジネスをする上で情報の取り方と捉え方はとても大切なので、情報感度の高さや、自分の意見を持てる人を僕は高く評価しています。
また、自分の意見を持っている人ほどTwitterでのフォロワー数も多く、仕事に対する情報感度も高い傾向があるので、SNSやニュースの見方や意見の発信については日頃から鍛えておくと良いと思います。
決して「フォロワー数が多いほうが良い」という話ではなく、「情報の取り方」と「発信のやり方」が大事なので、聞いてもいないのに「僕はフォロワー1,000人います」とかは言わないほうがいいです。※ここの認識も間違っている人が多いです。
転職エージェントにおける面接対策の流れ
ここまで具体的な質問と回答について解説してきましたが、こうした面接対策は転職エージェントでも行ってもらえます。ここからは転職エージェントとの面談で準備するべきことについてもお伝えします。
面接対策までに聞かれること
転職エージェントが面談で聞かれるのは下記の6つです。転職エージェントに転職相談を行う際は、事前に以下の6ポイントを整理しておくとスムーズに進みます。
1. 転職理由
2. 希望の業界・職種
3. 今までの職務経歴・強み・実績
4. 現在の年収・希望年収
5. 現在の転職活動状況
6. 希望する転職時期
事前に準備できればベターですが、時間がなかったり一人で整理するのが難しい場合は面談時に相談する形でも構いません。
転職エージェントとの面談の流れは下記です。
1:自己紹介
まずはお互いに自己紹介をします。転職エージェントは自社の特徴やサポート実績、今後のプラン、またエージェント本人のキャリアやサポート実績、サポートを得意とする分野などについても説明があるかと思います。ここで気になることがあればエージェントに質問をしてかまいません。あなたの転職をサポートするのに合っているのか確認しておきましょう。
2:職務経歴・仕事の内容の確認
あなたの用意した履歴書・職務経歴書をもとにこれまでのあなたのキャリア・スキルを掘り下げていきます。エージェントからの客観的な意見をもらうことで、あなた自身が気づいていないアピールポイントや強みを知ることができるいい機会になります。それによって転職の選択肢も広がる可能性もあります。
3:転職理由や今後の希望のキャリアをヒアリング
次にあなたの転職理由や転職を希望する職種や業種についてヒアリングを行います。この時点で希望の職種や業種が決まっていなくても大丈夫です。エージェントがあなたの転職理由から次の転職先を選ぶ際に重視すべきこと・仕事観などを紐解き、あなたの目指すキャリアとどういった職場があなたに合っているのか一緒に考えていきます。
4:転職先に関する希望条件
転職するにあたり、あなたが転職先に求める年収、勤務形態、福利厚生などを整理していきます。転職してから後悔しないためにも正直に希望する条件を伝えて構いませんが、あまり多く条件を挙げすぎると紹介してもらえる求人案件が少なくなる可能性がありますので注意してください。
5:求人案件の紹介
ここまでのヒアリングを踏まえ、エージェントからあなたに合った求人案件の紹介を受けます。転職エージェントを利用するメリットの1つとして、この段階であなたに紹介される求人案件に関しては求人票に記載されている情報に加え、企業の社風や福利厚生の取得率、など転職サイトや公式ホームページからでは知り得ない情報も教えてくれます。
気になる企業や不明な点があればエージェントに質問して細かく確認しておきましょう。
6:転職活動の今後の流れの説明
最後に今後の転職活動の流れや、あなたに合った求人が新たに発生すれば連絡する旨、また、紹介された求人案件の中にあなたが気になる案件があった場合の今後の流れなどの説明があり、面談は終了となります。
7:職務経歴書の添削
気になる求人をエージェントに送ると、企業へ応募する前に書類の添削をしてくれます。職務経歴書や履歴書は転職エージェントに添削してもらうとスムーズに通過できる可能性があるので、迷わずに相談してみましょう。
また、本サイトでも『転職の専門家が教える“戦略的”職務経歴書の書き方(無料テンプレート付)』で解説しているので、合わせて読んでみてください。
8:面接対策
書類を通過すると、企業の面接対策を転職エージェントが行ってくれます。過去に出題された質問や内定をもらった人が面接で聞かれたことなどを教えてくれるので、必ず面接対策をしてもらってください。面接対策しないで受けるよりも内定率は確実に上がります。
リクルートエージェントは面接力向上セミナーの動画をYouTube限定公開しているほか、面接力向上セミナーイベントも随時開催しているので、ぜひ参加してみてください。
転職面接の注意点
転職エージェントはキャリアアドバイザー(担当者)ごとの差が大きくあります。例えどんなに仕事ができない転職エージェントにむかつくことがあっても、使わないほうが損をします。
転職エージェントが見ている求人のデータベースは全員同じです。つまり、こちらが「転職エージェントからどう求人を引き出すか?」がポイントになります。
「転職エージェントの担当がむかつくから、良い転職エージェントの担当者にあたるまで面談に行く」という人もいますが、その時間がもったいないので「各転職エージェントをどう使いこなすか」という視点で面談に臨むようにしてください。
転職エージェントとの面談で「自分が求める求人」を出してもらうには、転職エージェントに合った姿勢で面談に行くことが大切です。このあたりは「【面談】転職エージェントとのキャリア面談で伝える内容と回答のポイント」にまとめているので、合わせてご覧ください。
転職の面接対策に強い転職エージェント
転職の面接対策に強い転職エージェントをご紹介します。
1:doda
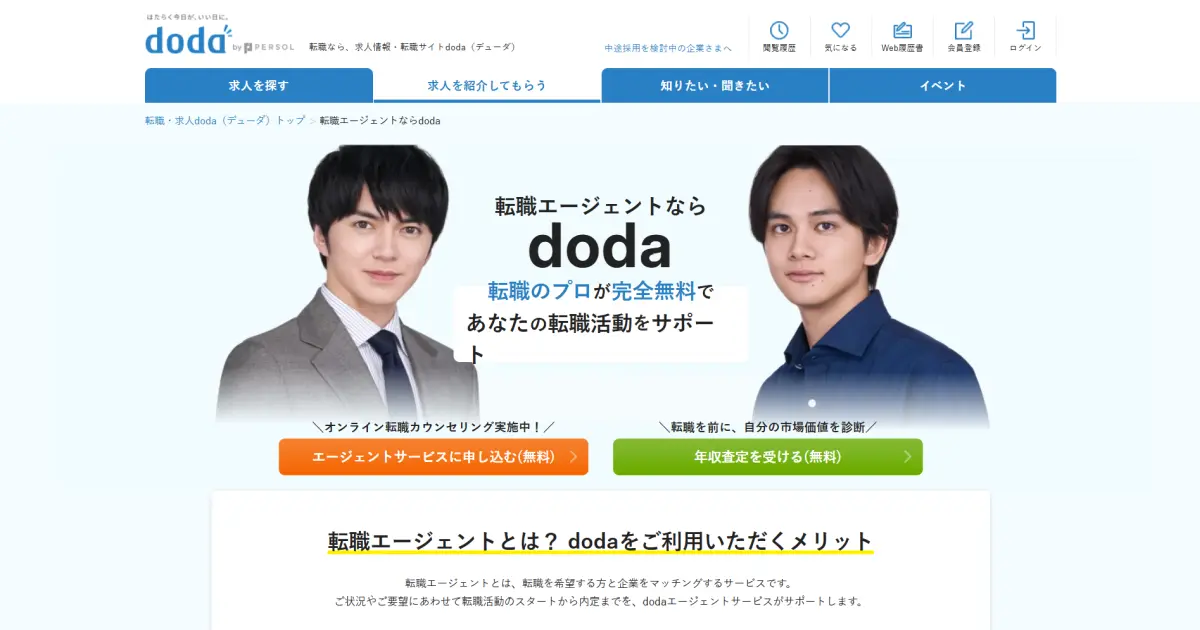
口コミ:doda 評判を確認
おすすめ度:★★★★★
公開求人数:270,049(2026年2月11日現在)
求人数増減:+1,648(先週比↑up)
【公式サイト】https://doda.jp/
面接対策に強いと定評があるのが『doda』です。『面接で必ず聞かれる5つの質問~回答例文と対策~』などを参考に、転職エージェントと面談対策をしてもらうことができます。
初めての転職であっても、キャリアアドバイザーのサポートを受けながら応募書類を作成から面接対策をできるため、より実践的な面接対策ができます。
出典:公式サイト
2:マイナビ転職エージェント

口コミ:マイナビ転職エージェント 評判を確認
おすすめ度:★★★★★
【公式サイト】https://mynavi-agent.jp/
面接対策に強い転職エージェントの2つ目は『マイナビ転職エージェント』。
マイナビ転職エージェントは「20代に信頼されている転職エージェント」として人気があります。2023年、2024年、2025年と3年連続でオリコン満足度ランキング1位を獲得しています。
『中途採用・転職面接の質問と回答例まとめ!流れやマナーもあわせて解説』にもあるように、転職エージェントの担当者が面接対策をしっかり行ってくれるため、初めて転職する方でも安心です。面接に自信がない人におすすめです。
※マイナビのプロモーションを含みます
出典:公式サイト
3:リクルートエージェント

口コミ:リクルートエージェント 評判を確認
おすすめ度:★★★★★
公開求人数:743,280(2026年2月11日現在)
求人数増減:+1,363(先週比↑up)
【公式サイト】https://www.r-agent.com/
初めての転職で面接対策に不安がある人におすすめ転職エージェントが『リクルートエージェント』。
『【面接の質問対策】転職の面接で必ず聞かれる質問と答え方のポイント』にもあるように、面接対策に非常に強く、セミナーなども開催しています。
土日でもしっかり対応してくれるため、面接対策悩んでいる人におすすめできます。転職面接後のフォローなどのにおいても満足度が非常に高いため、おすすめです。
出典:公式サイト
転職面接対策まとめ
私が面接でよく見ているポイントについてお伝えしましたが、面接に正解はありません。ですが、少なくともここに書いたポイントを話せるようにしておくことは、今後の自分のキャリアにおいて役立つ武器になると思うので、参考にしてみてください。
こちらの内容は私の書籍にもまとめているので、ぜひ読んでみてください。また合わせて「転職面接対策おすすめ本」の記事もご覧ください。
また、おすすめの転職サイト記事も合わせてご覧ください。
執筆者・監修者のmotoについて
![]()
moto
Follow @moto_recruit
起業家・著述家。実名は戸塚俊介。広告・人材・IT業界など8社へ転職。副業でmoto株式会社を起業し、上場企業へM&A。現在はHIRED株式会社(有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-313037)代表取締役。著書:『転職と副業のかけ算』(扶桑社)、『WORK』(日経BP)、YouTubeチャンネル:『motoの転職チャンネル』。